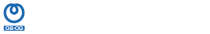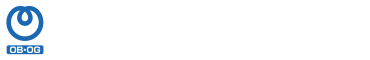沖縄の電信電話年表 (昭和20年~昭和62年)
![]() 本年表は戦後の電信電話年表を、私の独断と偏見で「沖縄の電信電話事業史」(琉球電信電話公社発行)及び「続沖縄の電信電話事業史」(沖縄電信電話管理局発行)から抜粋したものである。
本年表は戦後の電信電話年表を、私の独断と偏見で「沖縄の電信電話事業史」(琉球電信電話公社発行)及び「続沖縄の電信電話事業史」(沖縄電信電話管理局発行)から抜粋したものである。
沖縄の電信電話年表
(太平洋戦争終結後~本土復帰まで)
| 年次 | 沖縄の電信電話 | 社会一般 |
| 1945 (昭和20年) | (本島:1,426、宮古:50、八重山:68) | 沖縄戦おわる(6/23) 広島に原爆投下(8/6) 長崎に原爆投下(8/9) 太平洋戦争終結(8/15) 沖縄諮詢会(石川)設置(8/29) 通信部長:平田嗣一氏 |
| 1946 (昭和21年) | 沖縄民政府創立(4/22) 日本国憲法公布(11/13) (昭和22/5施行) | |
| 1947 (昭和22年) 1948 (昭和23年) 1949 (昭和24年) | - | |
| 1950 (昭和25年) | 琉球郵政庁発足(4/1) 琉球大学開学(5/22) | |
| 1951 (昭和26年) | 琉球臨時中央政府発足(4/1) | |
| 1952 (昭和27年) | 琉球政府発足(4/1) | |
| 1953 (昭和28年) | 1953年(S28年)頃までに再建ほぼ終わる | - |
| 1954 (昭和29年) | - | |
| 1955 (昭和30年) | - | |
| 1956 (昭和31年) | 沖縄全逓信労働組合結成(10/7) | |
| 1957 (昭和32年) | ソ連人工衛星打上成功(10/4) | |
| 1958 (昭和33年) | 米国人工衛星打上成功(2/11) | |
| 1959 (昭和34年) | (資本金:$200万、職員518名、琉球政府より引継ぐ) | 太子ご結婚式(4/10) 米軍Z機宮森小学校(石川市)に墜落死傷者121人(6/30) |
| 1960 (昭和35年) | アイゼンハワー大統領来沖(6/19) | |
| 1961 (昭和36年) | ケネディー大統領就任(1/20) | |
| 1962 (昭和37年) | - | |
| 1963 (昭和38年) | みどり丸那覇の西方海上で沈没:死者75人、行方不明43人(8/17) ケネディー大統領暗殺(11/22) | |
| 1964 (昭和39年) | 東京オリンピック開幕(10/10) | |
| 1965 (昭和40年) | 佐藤栄作総理大臣来沖(8/19) | |
| 1966 (昭和41年) | - | |
| 1967 (昭和42年) | - | |
| 1968 (昭和43年) | 霞ヶ関ビル完成(4/12) 初の行政主席公選 屋良朝苗当選(11/10) | |
| 1969 (昭和44年) | アポロ11号月面着陸(7/20) | |
| 1970 (昭和45年) | 赤軍派:日航機よど号 ハイジャック(3/31) | |
| 1971 (昭和46年) | 沖縄返還協定調印(6/17) | |
| 1972 (昭和47年) | 本土復帰:日本電信電話公社に組織編入(5月15日) (CS-10M方式) | 沖縄の施政権返還(5/15) |
| 1973 (昭和48年) 1987 (昭和62年) | - |
比嘉健二